童謡といえば、子どもたちが無邪気に歌うものというイメージがあります。
しかし、日本の伝統的なわらべうたの中には、よく聞くと不気味さを感じるものも少なくありません。
歌詞の意味が曖昧で、どこか不穏。
特に歴史的背景や地域に伝わる口承文化を辿ると、それぞれの歌がただの遊び歌ではないことに気づかされます。
今回はそんな「怖い童謡」の中から、特に有名で議論の多い5曲を取り上げ、その歌詞や背景に潜む闇を考察します。
単なる怖い話ではなく、日本文化の一端としての童謡の“裏の顔”をひも解いていきましょう。
日本の怖い童謡ベスト5!歌詞に潜む闇と都市伝説!
第1位|かごめかごめ

不気味な言葉と謎の多い歌詞
「かごめかごめ」は、意味不明な言葉や矛盾した時間表現(夜明けの晩)、幽霊を思わせる「後ろの正面」など、不気味な要素が満載の童謡です。
「かごの中の鳥」という比喩は自由を奪われた存在を連想させ、閉じ込められた魂や囚われの者を表す象徴とされています。
そのほかにも、「鶴と亀がすべった」といった吉兆を象徴する動物が倒れる描写は、幸運が崩れる様子や死の暗示と解釈されることがあります。
多様な解釈と都市伝説
この歌には、江戸時代の牢獄説、処刑説、さらには呪術的儀式歌としての側面まで、多くの説があります。
特に「誰が後ろにいるのか」という問いかけには、霊的な存在を探るような雰囲気が漂い、まるで降霊術を思わせます。
また、目隠しをして囲まれる遊びの構造自体が、選ばれた者に災いが降りかかるという呪術的構図に重なるとも言われています。
まさに、日本の童謡の中でも群を抜いて“闇が深い”存在です。
▶ 詳しくはこちら:かごめかごめが怖いと言われる理由とは?
第2位|通りゃんせ
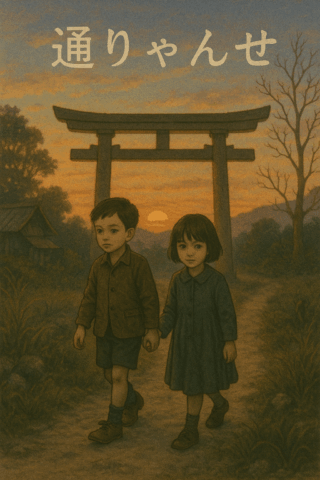
表と裏の意味を持つ童謡
「通りゃんせ」は、一見すると神社参拝の行き帰りを描いた歌のように見えますが、「行きはよいよい、帰りは怖い」というフレーズには不穏な響きがあります。
親が子どもを神社に連れていく様子とされますが、そこには何らかの“通過儀礼”のような重さを感じさせます。
特に、「帰り」が強調されていることは、何かしらの犠牲や危険を暗示しているように思えます。
また、この歌は「通してくだんせ」「この子の七つのお祝いに」など、特定の年齢や儀礼のタイミングを示している点も注目されます。
七歳というのは、昔の日本における“子ども”と“人間”の境目のような扱いをされていた年齢であり、そこには文化的・宗教的な意味合いが深く関係しています。
関所・死の比喩という説も
この「帰りは怖い」は、関所での取り調べや、死後の世界への旅を示唆しているという説もあり、子どもの生死にまつわる物語が隠されていると考えられています。
江戸時代の関所は厳しい警備体制を敷いており、通過するには正当な理由が必要だったため、その緊張感が「通りゃんせ」の世界観に影響を与えたとする説もあります。
さらに、地域によってはこの歌が“神に子どもを捧げる”風習と関係していたとも言われており、単なる遊び歌とは言い切れない側面があります。
子どもの命を神に差し出す風習や、病の快癒祈願を背景に持つともされ、神聖さと恐怖が共存する独特の雰囲気が漂います。
第3位|花いちもんめ
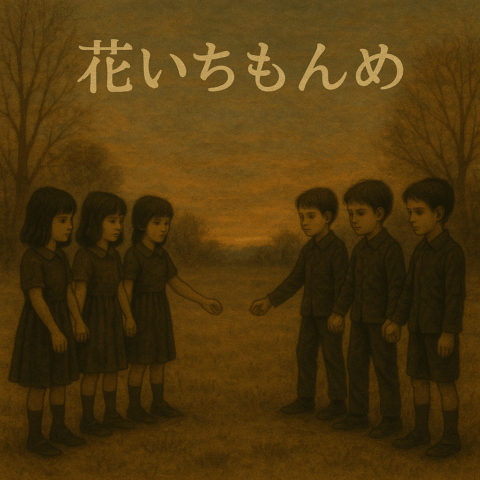
子どもを“選ぶ”遊びの背景
「花いちもんめ」は、子どもたちが二組に分かれて人を取り合う遊びの中で歌われる童謡です。
「あの子がほしい、あの子じゃわからん」といったやり取りは、単なる遊びとは思えない、どこか“取引”的な印象を与えます。
遊びの中で人を選び合うという行為は、社会における選別や排除の構図を模倣しているようにも見え、その無邪気さの裏に大人社会の縮図が浮かび上がります。
さらに、歌の中で繰り返される交渉のリズムは、子どもたちに“選ばれる・選ばれない”という価値基準を無意識に植え付けていた可能性もあります。
そうした側面から、「花いちもんめ」は現代でも教育的観点から議論されることがあります。
遊女取引や奉公人との関係?
この歌には、かつての遊女の選定や、貧困家庭から子どもが奉公に出される様子を暗示しているという説もあります。
江戸時代や明治期に存在した「口入れ屋(仲介業者)」による労働者の斡旋の様子が、歌の形式に反映されているとも考えられています。
中には、「花いちもんめ」の“花”が遊女を意味し、“一文目”が価格の交渉を示しているという解釈もあります。
子どもの無邪気な声で交わされるこのやり取りの裏には、当時の社会制度や生活苦が反映されているのかもしれません。
そうした背景を知ることで、単なる遊び歌が社会史の一端を語る資料に変わっていきます。
第4位|ずいずいずっころばし
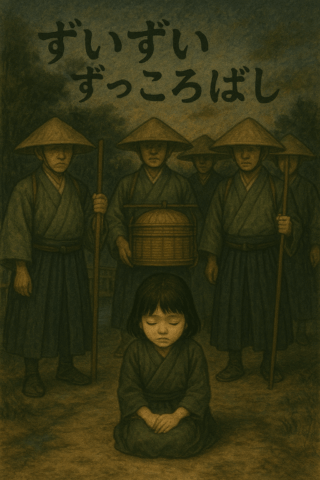
意味不明な言葉が不安を煽る
「ずいずいずっころばし ごまみそずい」という語感豊かな歌い出しは、意味を深く考えなければ楽しく聞こえますが、実際にはその内容が極めて謎に包まれています。
この歌詞に含まれる言葉の多くは現代では使われないもので、語源や意味が不明瞭なものも多く、それが一層の不気味さを感じさせます。
また、「茶碗にお茶を注いで…」と続く歌詞も、一見ほのぼのとした日常描写のように見えて、背景にある状況がまったく不明なため、逆に空恐ろしさを覚える人もいます。
言葉に意味があるのか、それともただの音遊びなのか、その曖昧さが不安感を呼び起こします。
背景にある密会や悲劇
その裏には、茶屋での密会、子どもを守るための大人たちの策略、あるいは子どもが犠牲となった事件が隠されているという説も存在します。
「とっぴんしゃん」といった音の響きにも不穏さがあり、繰り返されるリズムと奇妙な言葉が、不安や不気味さを助長する要因となっています。
さらに一部の説では、この歌が“子どもを黙らせるための歌”であり、大人の世界の暗黙の了解や秘密を伝えないようにするための、ある種の口止め歌だったとも言われています。
そう考えると、無邪気な遊び歌の背後に、社会の裏面が静かに横たわっているようにも感じられるのです。
第5位|あんたがたどこさ

地名が語る軍事的背景
「肥後さ」「せんば山」など、具体的な地名が登場するこの歌は、一見するとご当地童謡のように感じられますが、背景に軍事的な要素があるという説も根強くあります。
特に「肥後」は現在の熊本県であり、その中心には熊本城という戦国時代からの要所が存在していました。
熊本城は、戦時には兵士の訓練や防衛の要とされた場所であり、童謡に登場する地名が偶然とは思えないという指摘があります。
このように、歌詞に登場する地名を手がかりに歴史的背景を紐解くことで、単なる子どもの遊び歌にとどまらない奥深い意味を見出すことができます。
実際に、軍用地としての「せんば山」周辺にはかつて訓練場や武器庫があったという記録もあり、地域の軍事的役割と結びつけて解釈されることが多いのです。
戦時下の隠された意味
特に熊本城の存在や、軍事訓練に関連した場所との関係が語られ、「たぬきがいたから撃ち殺した」という描写は、単なる動物退治ではなく戦争や処刑のメタファーとも考えられています。
たぬきは古くから化ける動物として知られ、真実を隠すもの・偽装の象徴と捉えられることもあります。
そのたぬきを「撃ち殺す」ことは、敵対者を排除する行為や、スパイの粛清と重ね合わされる場合もあるのです。
また、こうした戦時下の暗喩は、明るくテンポのよいメロディによってカモフラージュされ、子どもたちが自然に口ずさめる形で日常に浸透していきました。
結果として、童謡の形をとりながら、社会における恐怖や不安、時に忠誠心といった価値観を無意識のうちに伝えていたのかもしれません。
まとめ|童謡に込められた“もうひとつの日本史”
これらの童謡に共通するのは、「意味の曖昧さ」「不穏なワード」「民間信仰との関わり」といった要素です。
無邪気に聞こえる歌の中に、時代の影や人々の死生観、社会の価値観が見え隠れします。
また、これらの歌が伝承によって各地域で変化している点も重要です。
童謡とは単なる遊び歌ではなく、時に“語られなかった歴史”や“失われた習俗”を伝える文化資料でもあります。
今一度、身近にある童謡の歌詞に耳を傾けてみると、その奥に広がる世界が見えてくるかもしれません。
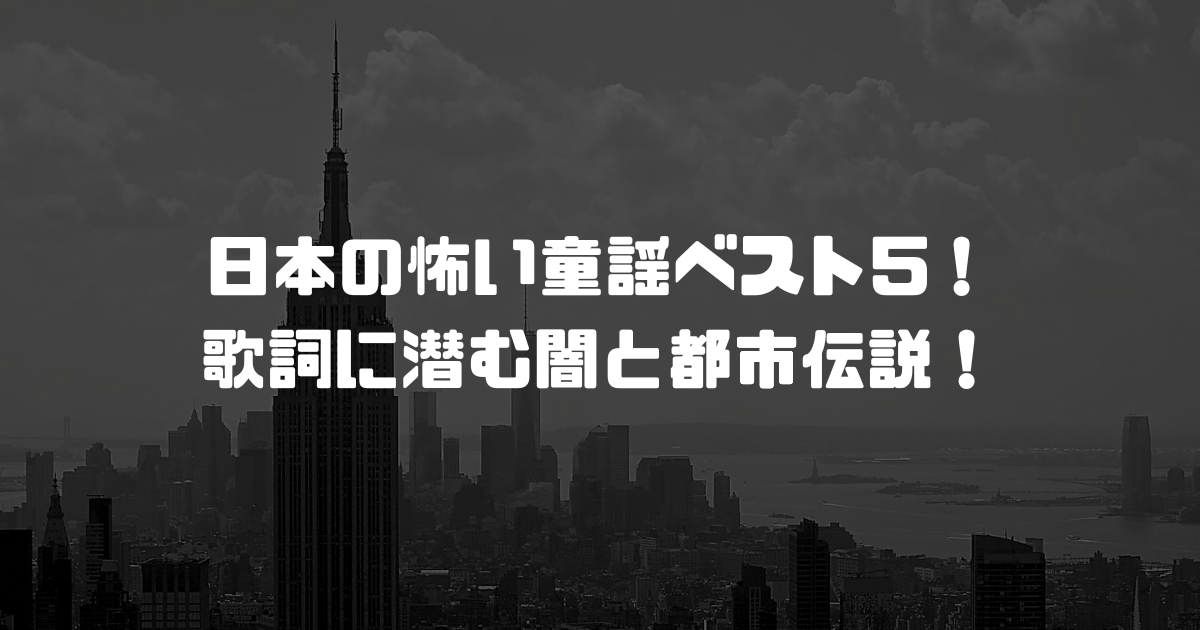

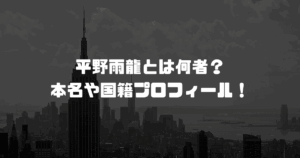
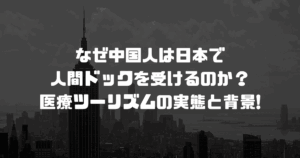
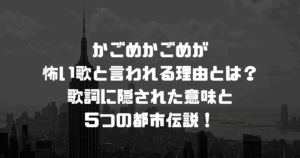
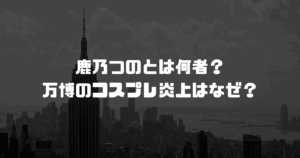
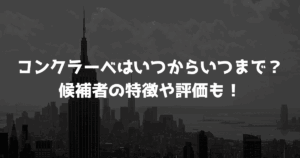
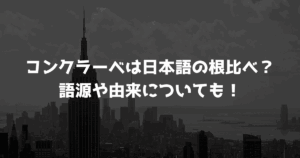
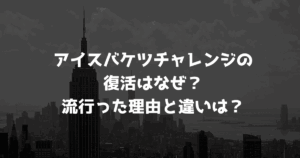
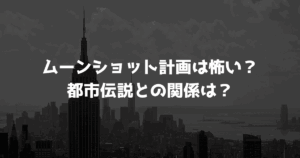
コメント