「国内は増税や物価高で厳しいのに、海外には何千億円も支援?」
そんな声が広がる中、
2025年に外務大臣に就任した岩屋毅(いわやたけし)氏が、わずか3か月あまりの間に行った海外支援の金額が注目を集めています。
フィリピンやバングラデシュといったアジア諸国をはじめ、国連機関への多額の拠出など、その総額はなんと4,000億円を超える規模です。
「どの国に、いくら支援したのか?」「過去の外務大臣と比べて本当に多いのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、岩屋外務大臣が海外支援した国とその金額を一覧でわかりやすくまとめるとともに、過去との比較や背景についても解説していきます。
岩屋外務大臣が海外支援した国と金額一覧!
5月29日、#岩屋外務大臣 は、日経フォーラム第30回「アジアの未来」の晩餐会に出席し、挨拶を行いました。https://t.co/iBvAJ6npws pic.twitter.com/tzRek3Lhed
— 外務省 (@MofaJapan_jp) May 29, 2025
岩屋毅氏が外務大臣に2025年3月に就任してから海外支援した国と内容を時系列順にまとめました
| 対象国・機関 | 内容 | 金額(億円) | 日付 |
|---|---|---|---|
| UNRWA | 人道支援拠出 | 502.70 | 2025年3月 |
| バングラデシュ | 経済改革・気候対策、鉄道複線化(円借款) | 1,520.77 | 2025年3月 |
| フィリピン | 気候・保健・インフラ(円借款) | 1,715.80 | 2025年3月 |
| ナイジェリア | スタートアップ・施設支援(無償) | 47.76 | 2025年3月 |
| トルコ | 女性職業訓練・校舎改修(無償) | 0.63 | 2025年3月 |
| ベトナム | ジェンダー支援(NGO連携無償) | 2.50 | 2025年3月 |
| スーダン | 食料安全保障(食糧援助) | 1.50 | 2025年3月 |
| UNICEF(ユニセフ) | 人道支援拠出 | 559.60 | 2025年3月 |
| ウガンダ | カルマ橋架け替え(無償) | 49.39 | 2025年3月25日 |
| UNHCR(ベネズエラ難民) | 女性支援(無償) | 1.04 | 2025年3月25日 |
| ブラジル | 自然災害対策(無償) | 1.047 | 2025年3月26日 |
| フィジー | 気象向上・防災(無償) | 17.39 | 2025年3月27日 |
| カンボジア | 環境教育(無償) | 0.29 | 2025年3月27日 |
| IOM | バングラ避難民支援(無償) | 5.02 | 2025年4月27日 |
| フィジー | 災害対応(無償) | 17.65 | 2025年5月6日 |
| 西アフリカ地域 | インフラ整備(協調融資) | 327.60 | 2025年5月15日 |
| カンボジア | 体育教員養成・若者支援(無償) | 1.7 | 2025年5月20日 |
| ガーナ | 人材育成奨学計画(無償) | 4.02 | 2025年6月2日 |
合計は 約4,216.81億円になります。
の他にも、シリアへの緊急援助10百万ドル(約13~14億円)などもありますが、上記期間中の主要支援内容です。
岩屋外務大臣の海外支援はおかしい?
岩屋外務大臣が就任してからのわずか3か月間で、海外支援総額は4,000億円超にのぼります。
これは、日本が通常1年間に行うODA(政府開発援助)の約3分の1に相当する金額です。
過去の外務大臣が1四半期あたりに支出した海外支援額はおおむね2,000~3,000億円程度であり、それに比べて今回のペースは明らかに突出しています。
とくに注目すべきは、バングラデシュやフィリピンなど、1,000億円を超える大型支援案件が短期間に集中したことです。
こうした規模感の支援が連続して行われるのは、非常に異例といえるでしょう。
なぜこれらの国が支援先に選ばれたのか?
今回の支援先には、東南アジアやアフリカの新興国、そして国連関連機関などが多く含まれています。
これにはいくつかの理由があります。
1. インフラ整備と経済成長の後押し
バングラデシュやフィリピンといった国々は、インフラの老朽化や人口増加による社会課題を抱えています。
日本としては、円借款を通じてインフラ投資を支援することで、現地経済の安定化と日本企業の参入を後押しする狙いがあります。
2. 安全保障と人道的配慮
ナイジェリアやスーダンなどは、紛争や自然災害の影響で社会基盤が脆弱になっています。
こうした地域に対して日本は、「人間の安全保障」を重視した支援を行っており、国連機関や国際NGOを通じた人道支援も積極的です。
3. 気候変動と災害対策
フィジーやカンボジアなどへの支援では、気候変動に伴う災害リスクへの備えが重視されました。
とくに太平洋諸国においては、台風や海面上昇といった自然の脅威が深刻な問題であり、日本の技術やノウハウが貢献できる分野でもあります。
財政が厳しいのに、海外支援って必要?
「日本の財政は厳しい」と言われる中で、海外に数千億円もの支援をすることに疑問を持つ方は少なくありません。
実際、増税や社会保障の見直しが議論されている今、なぜそれでも海外支援を優先するのでしょうか?
その理由のひとつは、日本の外交戦略にあります。
海外への支援は、ただの“お金のばらまき”ではなく、日本と各国との信頼関係を築いたり、安全保障や経済的な影響力を維持するための重要な手段なのです。
特にインフラ支援などは、日本企業の進出にもつながり、将来的な経済利益をもたらす可能性があります。
もちろん、国内の生活支援や教育・医療への投資も大切です。
しかし、海外支援は長期的に見れば「世界の安定=日本の安定」につながる面もあるため、一定の意義があるといえるでしょう。
つまり、短期的には疑問に感じるかもしれませんが、外交的・経済的な戦略を含んだ行動であることを理解することが大切です。
岩屋外務大臣の海外支援でのメリットとデメリットは?
海外への大規模な支援は、単に相手国を助けるだけでなく、日本にとってもさまざまなメリットやデメリットがあります。
ここでは、それぞれの側面をわかりやすく整理してみましょう。
メリット
- 外交的信頼の構築
海外支援を行うことで、国際社会での日本の存在感や信頼が高まります。災害時や安全保障上の連携にもプラスになります。 - 経済的リターン
インフラ整備の円借款などは、日本企業がプロジェクトに関与することも多く、将来的な経済効果が期待できます。支援先の安定は、日本への投資や貿易にもつながります。 - 地政学的な影響力の確保
中国や他の大国が影響力を強める中、日本も同様にアジアやアフリカなどでの発言力を維持するため、支援は戦略的に重要です。
デメリット
- 財政的な圧迫感
国民からすると「そのお金を国内に使ってほしい」という思いも強く、特に増税や物価高のなかでは不満につながりやすいです。 - 支援の成果が見えにくい
海外支援は即効性があるわけではないため、目に見える効果が実感しづらく、「本当に役立っているのか?」と疑問視されることもあります。 - 不適切な使われ方のリスク
相手国の制度やガバナンスによっては、支援が汚職や不透明な事業に流用される懸念もあります。
このように、海外支援には日本にとっての戦略的な利点がある一方で、国民の実感とのギャップや成果の不透明さという課題も抱えています。
メリットとデメリットを冷静に比較したうえで、今後の支援方針をどう評価するかが重要になってきます。
岩屋外務大臣の海外支援のお金は返ってくる?
岩屋外務大臣の海外支援のお金は「全部が貸し出し(=返ってくる)」ではありません。
日本の海外支援(ODA)は、主に以下の3つの形があります。
| 支援の種類 | お金の性質 | 返ってくる? | 内容の概要 |
|---|---|---|---|
| ① 円借款(えんしゃっかん) | 貸す(低金利) | 基本的に返ってくる | インフラ整備など大規模プロジェクト向け。年利0.1〜1%程度で数十年かけて返済される。 |
| ② 無償資金協力 | あげる(返済不要) | 返ってこない | 教育、医療、防災、人道支援など。相手国の返済能力がないときに行われる。 |
| ③ 技術協力 | ノウハウや人材の派遣 | お金ではない | JICAの専門家派遣など。技術や制度を伝える支援。 |
円借款による海外支援一覧(返済されるタイプ)
- バングラデシュ:経済改革・気候対策、鉄道複線化|1,520.77億円(2025年3月)
- フィリピン:気候・保健・インフラ|1,715.80億円(2025年3月)
- 西アフリカ地域:インフラ整備(協調融資)|327.60億円(2025年5月15日)
円借款の合計金額は3,564.17億円になります。
無償資金協力による海外支援一覧(あげたお金)
- UNRWA:人道支援拠出|502.70億円(2025年3月)
- フィジー:災害対応|17.65億円(2025年5月6日)
- IOM:バングラ避難民支援|5.02億円(2025年4月27日)
- カンボジア:環境教育|0.29億円(2025年3月27日)
- フィジー:気象向上・防災|17.39億円(2025年3月27日)
- ブラジル:自然災害対策|1.047億円(2025年3月26日)
- UNHCR(ベネズエラ難民):女性支援|1.04億円(2025年3月25日)
- ウガンダ:カルマ橋架け替え|49.39億円(2025年3月25日)
- UNICEF:人道支援拠出|559.60億円(2025年3月)
- スーダン:食料安全保障(食糧援助)|1.50億円(2025年3月)
- ベトナム:ジェンダー支援(NGO連携)|2.50億円(2025年3月)
- トルコ:女性職業訓練・校舎改修|0.63億円(2025年3月)
- ナイジェリア:スタートアップ・施設支援|47.76億円(2025年3月)
- カンボジア:体育教員養成・若者支援|1.70億円(2025年5月20日)
- ガーナ:人材育成奨学計画|4.02億円(2025年6月2日)
無償資金協力の合計金額は1,212.24億円です。
岩屋外務大臣が実施した海外支援のうち、約75%が“貸し出し型”の円借款で、残り約25%が返済不要の無償資金協力という構成です。
まとめ
岩屋外務大臣は就任からわずか3か月で4,000億円以上の海外支援を実施し、その多くは円借款による戦略的な投資です。
一方で、返済不要の無償資金協力も含まれており、国民の間では賛否が分かれています。
外交的な信頼構築や経済的な波及効果を見据えた支援である一方、国内の生活支援とのバランスをどう取るかが、今後の大きな課題といえるでしょう。
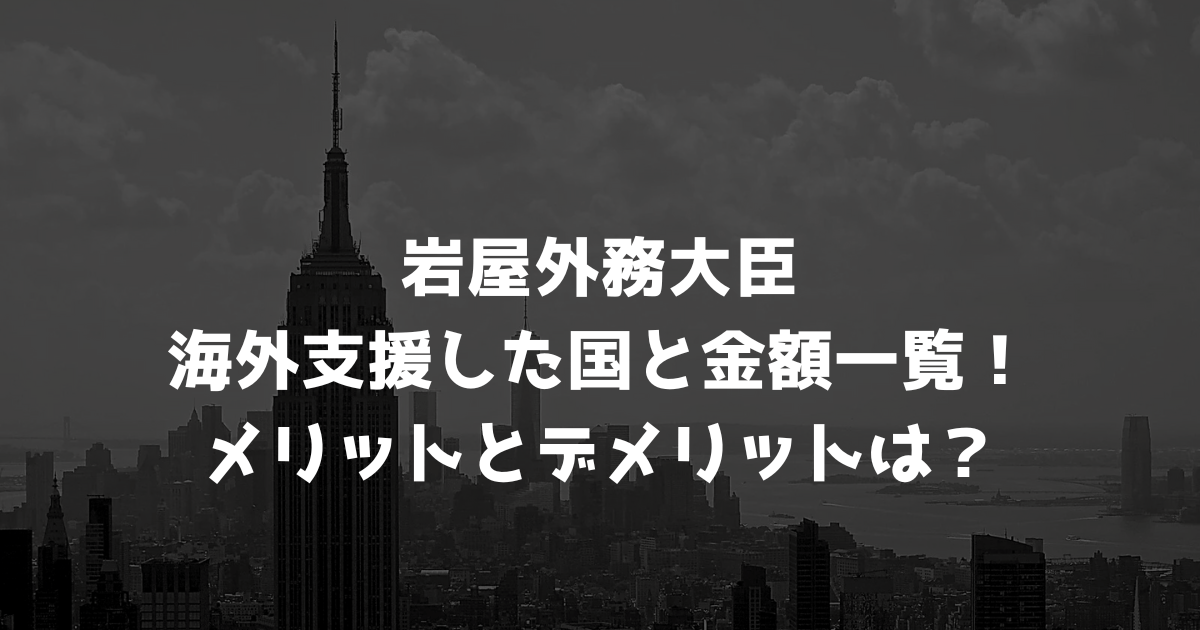
コメント