2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」は、発表直後から日本国内外で大きな反響を呼びました。
その不思議なビジュアルと奇抜なコンセプトは、多くの人々の目を引く一方で、SNSなどを中心にさまざまな憶測や批判も巻き起こりました。
中でも「デザイナーは誰なのか?」「なぜ逃げたと噂されているのか?」「既存作品のパクリなのでは?」といった疑問の声が多数見られます。
本記事では、そうした疑問に対して事実をもとに答えながら、ミャクミャクに込められたメッセージ性や社会的な意義についても詳しく掘り下げていきます。
ミャクミャクの正式なデザイナーは誰?
ミャクミャクの公式なデザインを担当したのは、デザイナーであり絵本作家でもある山下浩平(やました こうへい)さんです。
2022年に公式発表されたこの情報により、それまで曖昧だった「誰が作ったのか」という疑問に明確な答えが示されました。
山下浩平プロフィールと経歴!
山下氏は1971年生まれ、大阪芸術大学美術学科出身。
独自の世界観を持ち、絵本やキャラクターデザイン、インスタレーションなど多岐にわたる作品を発表しています。
代表作には『やまのくじら』などがあり、その幻想的で少し風変わりなタッチは、ミャクミャクのビジュアルにも通じるものがあります。
ミャクミャクのデザインコンセプト
ミャクミャクのデザインの基盤となったのは、「変化し続ける存在」というコンセプト。
赤と青の液体のような体、触手のような手足、無数の目が浮遊するようなデザインは、明確な「型」を持たず、多様性を象徴しています。
このデザインには、「未来の生命」「既存の価値にとらわれない創造」というテーマが込められており、「気持ち悪い」と感じさせること自体が、既存価値への挑戦といえるのです。
株式会社インラボとの関係は?
株式会社インラボ(INLabo)は、ミャクミャクの制作過程においてディレクションや広報、アートディレクション全般を担っていたクリエイティブチームです。
直接のキャラクターデザインは担当していないものの、プロジェクト全体のトーンやビジュアルの世界観づくりに関与しており、その存在は非常に大きなものでした。
インラボは、万博関連のビジュアル制作全般に携わっていたため、「ミャクミャクをデザインしたのでは?」という誤解が広がる要因にもなったと考えられます。
インラボの役割と誤解の理由
ミャクミャク発表当初、公式資料やメディアには「インラボ」が制作に関わったと明記されていたことから、多くの人が「インラボ=デザイナー」と理解してしまいました。
その一方で、キャラクターの細部のデザインや発想は山下浩平さんが個人として手がけたことが後に明らかになり、情報の伝達方法による混乱が原因だったといえます。
また、「インラボ」の名前が先に露出したことで、デザイナー個人がメディアに出たがらない、あるいは意図的に名前を伏せたのではないかといった憶測が飛び交い、「責任回避なのでは?」という疑念を呼びました。
こうした誤解は、プロジェクト全体の説明不足や情報整理の甘さが招いたものになります。
千原徹也氏の関与
インラボを率いるアートディレクター・千原徹也氏(株式会社れもんらいふ代表)は、万博全体のビジュアルブランディングを統括する立場にあります。
彼の名前が広く知られていることから、千原氏がミャクミャクのデザイナーだと勘違いする声も一部にありました。
しかし、千原氏自身はキャラクターの原案には関与しておらず、「世界観づくりの補完役」という立場にとどまっています。
このように、大規模なクリエイティブプロジェクトでは複数のチームや専門家が役割を分担することが一般的ですが、それが必ずしも一般ユーザーに伝わりやすいとは限らず、誤解を招く原因になる場合があるようです。
ミャクミャクのデザイナーの逃亡説はなぜ?
ミャクミャクの登場直後、ネット上で急速に拡散されたのが「デザイナー逃亡説」と呼ばれる噂です。
この憶測は、デザインに対する激しい賛否と、公式発表時にデザイナー個人の名前が明かされなかったことが重なり、人々の不安や疑念を煽るかたちで生まれました。
特にSNS上では、「責任を取らずに逃げたのでは?」「メディアに顔を出せない理由があるのでは?」といった投稿がバズり、多くの人に事実として受け入れられてしまった側面があります。
発表初期の情報不足が招いた誤解
多くの人々がミャクミャクのビジュアルをSNSやニュースサイトで初めて目にした際、その奇抜で斬新なデザインに対して驚きや戸惑い、不快感すら抱いたという声が多数見られました。
従来の「ゆるキャラ」的な親しみやすさとは異なり、どこか不気味さや異質さを感じさせるミャクミャクは、強烈な印象とともに議論を呼びました。
そのタイミングで、誰がデザインしたのかという情報がすぐに提供されなかったことで、「なぜ制作者の名前を明かさないのか?」「批判を恐れて隠れているのでは?」という不信感が生まれ、さらにそれが「逃亡したのではないか」という極端な解釈へとつながっていったのです。
情報公開の遅れや不透明さが誤解を生む典型例といえるでしょう。
実際の制作体制
実際のところ、ミャクミャクの制作には複数のチームとクリエイター、さらに広報や管理を担当するディレクター陣が関わる、大規模なプロジェクト体制が敷かれていました。
このような体制においては、まず法人や制作チームの名前が表に出されるのが通例であり、個人名が後から明かされるというのは珍しいことではありません。
広報発表の段階では、チーム単位での紹介にとどまっていたため、一般の視聴者には制作者不在のように見えてしまい、これがさらなる誤解を招いたと考えられます。
決してデザイナーが“逃げた”わけではなく、あくまで組織的な発表手順の一環であり、ミスリードがSNS上で一人歩きしてしまった結果だったのです
ミャクミャクのデザイナーのパクリ疑惑の真相とは?
ミャクミャクのビジュアルを見て、「どこかで見たような気がする」と感じた人は少なくありません。
こうした“既視感”が一部の人々に「パクリでは?」という印象を与え、SNSやネット掲示板などを中心に疑惑が拡散されることとなりました。
特にビジュアルが強烈であればあるほど、人は無意識に記憶にある何かと結び付けようとする傾向があります。
そのため、ミャクミャクのように抽象的かつ非現実的なデザインは、既存のキャラクターや芸術作品と重ねて語られやすいのです。
比較されたキャラクターとイメージの類似
ミャクミャクが比較対象として挙げられたキャラクターには、著名なものも多数含まれています。
たとえば「ムンクの叫び」に見られるうねるような形状や不安定な感情表現、「映画『AKIRA』」の変異する肉体の描写、「ポンキッキ」のガチャピンに似た丸みのあるフォルムなどが指摘されました。
また、「不気味かわいい」ジャンルに属する他のマスコットや、海外アニメのモンスター系キャラクターと比べる声もありました。
ただし、こうした類似は主観的なものであり、造形的・構造的な分析を行えば、それぞれのキャラクターとの共通点はごく表面的なものであることが明らかです。
色使いやシルエットが似て見えるという印象はあっても、設定や背景、表現意図まで含めて同一であるという証拠はなく、創作としての独自性はしっかり保たれています。
デザインの独自性
ミャクミャクは、最初から「理解されにくさ」や「不可解さ」を含んだ存在として設計されたキャラクターです。
「正体不明」「可変性」「不完全性」など、一般的なキャラクターデザインの“わかりやすさ”とは反対の要素をあえて盛り込み、それを特徴としています。
これは、万博という“未来志向”の場において、「固定概念からの脱却」や「多様性の受容」を象徴するキャラクター像を追求した結果といえるでしょう。
実際、山下氏は「人々の反応が二分することを前提に設計した」と語っており、万人に受け入れられることよりも、「賛否を巻き起こす力」こそが現代におけるキャラクターの価値であるという哲学が根底にあることがうかがえます。
その意味で、ミャクミャクは意図的に“似ているようで似ていない”不思議な存在としてデザインされており、パクリというよりはむしろ、“問いかけを投げかけるアート作品”と捉える方が適切かもしれませんね。
ミャクミャクに対する評価の変化は?
時間の経過とともに、ミャクミャクへの世間の印象は大きく変化しています。
最初は戸惑いや否定的な声が多かったものの、徐々に受け入れられ、今では「愛されキャラ」としての地位を築きつつあります。
初期の否定的反応
特にミャクミャクの発表初期には、「気持ち悪い」「子どもが泣く」「誰得?」といった否定的なコメントが多数寄せられました。
「ゆるキャラ的な親しみ」を期待していた人々にとって、ミャクミャクは予想外すぎたのかもしれません。
徐々に広がる共感と人気
しかし、イベントへの登場やグッズ販売などを通じて、ミャクミャクに触れる機会が増えるにつれ、「クセになる」「逆にかわいい」という共感が広がり始めました。
ファンアートやSNSでの“ミャク活”も盛んになり、今では一定の人気を誇る存在になっています。
まとめ
ミャクミャクは、現代社会の「多様性」や「対話」の象徴としてデザインされた、ただのマスコットを超えた存在です。
その見た目は、あえて一目で好かれにくい造形となっており、“わかりづらさ”や“違和感”すらも意図的に盛り込まれています。
このようなアプローチは、万人受けするキャラクターとは異なり、議論や解釈を生み出すことを目的としており、批判や誤解も含めて「話題になること」自体がデザインの狙いでもあります。
SNSで拡散された逃亡説やパクリ疑惑も、そうした誤解の延長線上にありましたが、議論を経て、むしろ共感を集める存在へと変化しつつあります。
2025年の大阪・関西万博を象徴するにふさわしいキャラクターとして、今後も注目されていくことでしょう。
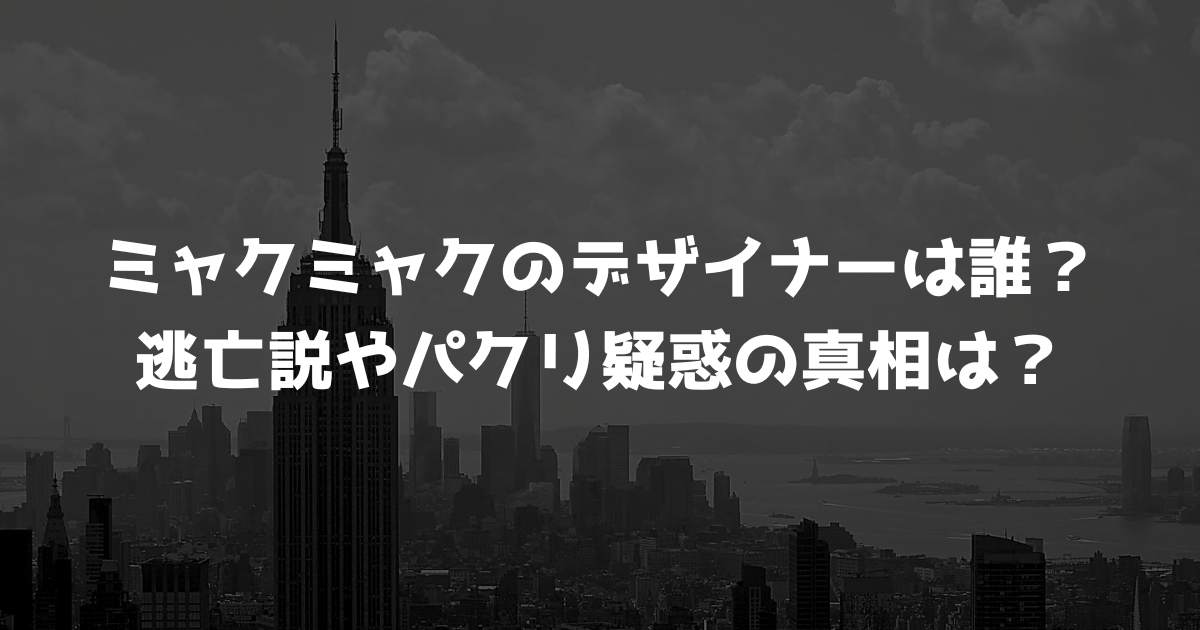
コメント